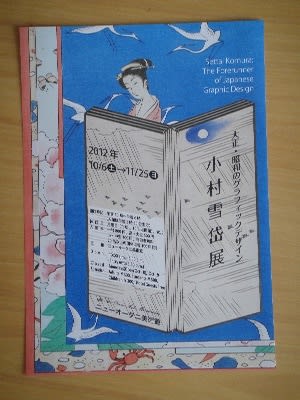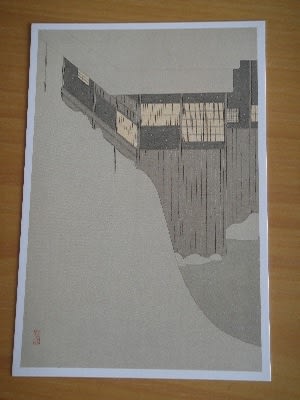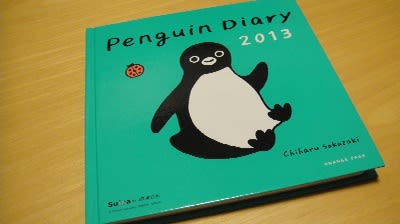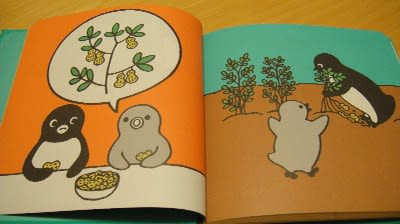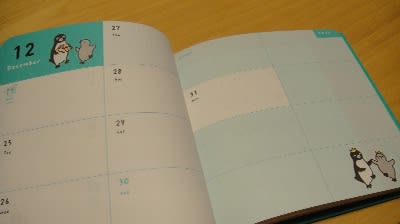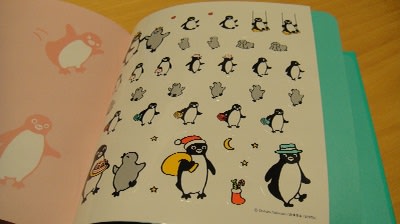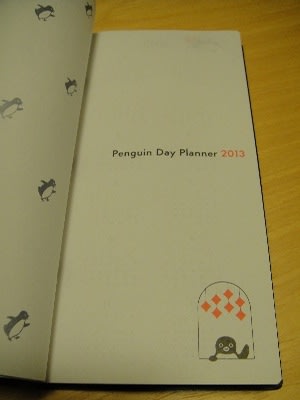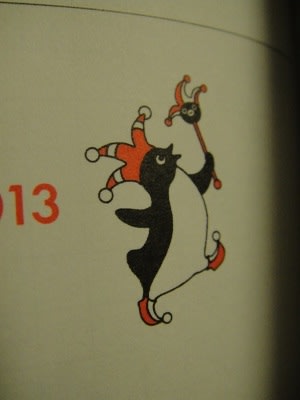![]()
東京国立近代美術館で開催中の「美術にぶるっ! ベストセレクション 日本近代美術の100年」に行ってきました。
記事にするのが遅くなってしまいましたが11/7に開催された夜間特別観覧会でじっくりと鑑賞して参りました。
(うわ!もう一ヶ月も経ってしまったとは。)
会場は二部構成となっていて第一部「MOMATコレクションスペシャル」(4F〜2F)、第二部「実験場1950s」(1F)と全館を使ってのボリュームのある展示。
当日は二時間かけてペース配分して見たものの時間が足りないくらいだなあと。
正直、この二部構成はばらしてそれぞれの展示としてもよかったのでは。
冒頭からの順序に従って気になった作品について書いてみたいと思います。
※写真の撮影、掲載については主催者の了解を得てあります。
展示室1 ハイライト
![]()
菱田春草「賢首菩薩」(写真中央)
春草の作品にはついつい吸い寄せられてしまいます。
お坊さんなんだけどもかわいくもありかつ気品もかんじさせてくれる。
色彩と精緻な描写、密と疎のバランスの配分。
ずっと見ていられる安定感。
横山大観の「生々流転」は独り占め出来て大満足。
水墨テクニックをこれでもかと投入して制作されていることが確認出来る。
とにかくここまで長い巻物はちょっとなく見応え十二分。
展示室2 はじめの一歩
![]()
土田麦僊「湯女」「舞妓林泉」
麦僊のこの2点、色味がものすごく好み。
どちらも赤と緑という補色同士、対極の色を同じ画面に配していながらもキツくならずにむしろふんわりとした印象が残るのが素敵。
そして何より決して古びて見えないのが素晴らしい。
展示室3 人を表す1
![]()
フジタの絵は線がシャープながらもほっこりとする。
なんだろう、自分の好みなのか見てて安心する感じがする。
あと画面に猫が登場してるのは大きいなあと。
展示室4 人を表す2
![]()
新海竹太郎「ゆあみ」
彫刻のコーナーの中でも特に惹かれました。
肌に貼り付く濡れたたタオルの質感に目がいく。
彫刻ではあるのだけどもなんだかいけないことをしているかのような背徳感が湧いてくる感じが面白くもあり。
展示室5 風景を描く
![]()
写真中央の岸田劉生「道路と土手と塀」をじくりと見てしまいます。
なんでもない風景なんだけどももりあがったその坂の向こうを思い浮かべてしまうからでしょうか。
展示室6 前衛の登場
![]()
古賀春江「海」
何度となく見てるもののやはりいいなと思います。
こういうふうに他の作家の作品と居並んだ時にこそこの個性は光るなあと。
コラージュ的に構成された画面が洗練されていて特異です。
![]()
谷中安規の版画、ぽかーんと抜けた感じがたまりません。
黒の他に、ほのかな色彩が乗って線と合っているなあと。
裸で自転車っていうが強烈に残ります。でもあくまでトーンはほのぼの。
展示室7 戦争の世紀に1
![]()
須田国太郎「歩む鷲」(写真左)
以前に見た時よりも俄然よく見える。須田の作品オンリーの中でよりもこういうふうに他の作家の作品との中に置かれてこそそのチカラが感じられるような気がしました。
佇まいが好きな作品です。
展示室8 戦争の世紀に2
![]()
藤田嗣治「サイパン島同胞臣節を全うす」、「アッツ島玉砕」
フジタ圧巻!!
「アッツ島玉砕」は画面にこれでもかと詰め込んだ兵士にくらくらとします。
「サイパン島同胞臣節を全うす」は構成が素晴らしい。戦争画なのだけどもそれぞれの役割の描写と配置がどことなく宗教画のように見える不思議な絵。
いつかは戦争画のみの展覧会が見てみたいものです。
展示室9 写真
![]()
森山大道の写真はやはり質感が好きなのだと思います。
写真は撮った作品からその写真家が分かるというのが一番なのだなあと実感。
植田正治の砂丘で撮ったシリーズなど個性の強さがぎゅっとつまっていたコーナーになっていたと思います。
展示室10 日本画
![]()
小倉遊亀「浴所その一」(写真左)
タイルの直線が湯で歪んで見える。浴槽の中の湯の緑が目に優しい。
直線が多い中で女性と湯が曲線で描かれていて引き立って見える。
![]()
福田平八郎「雨」、徳岡神泉「刈田」
山種美術館で見て以来、雨に再会。
ミニマムで構成された画面が光ります。なんてことない景色が何と美しいことか。
そして隣の刈田。
こちらはタイトルがなければ抽象画にも見えてくる。
切り取られた根のあたりが手のようなフォルム。
![]()
この椅子がなんとも雰囲気があってよかったです。
写真左奥の加山又造の春秋波濤は波の描写が面白い。
波濤のスクラッチした傷みたいな線の神経質な感じ、たまりませんね。
展示室11 疑うことと信じること1
![]()
横尾忠則のシルクスクリーンは圧巻!
左の「責め場」はエッヂの立った表現にズキリと来る。色彩のずらし加減でこうも効果的に響く。
右の人物のはどうしてもアプローチとしてウォーホルが脳裏をよぎってしまう。でも、よくみるとまるで違うんですよね。
草間彌生の作品はこのコーナーでは合ってなかったと言わざるを得ないなあと。
展示室12 疑うことと信じること2
![]()
高松次郎「No.273(影)」(写真右)
これは何度見ても好き。
そぎ落として線を減らすのは勇気が要る。
シンプルな構成のものだし一目見たら必ず残る。
画面左の奥も必見。作家というのは設計図を遺せばいいのだなあと。事実それで後にこういう展示も出来るのだなあと。
展示室13 海外作品とMOMAT
![]()
マックス・エルンスト「つかの間の静寂」(写真右下)
以前に横浜美術館でエルンストの展示(フィギュア×スケープ)を見た時にはあんまりいいと思わなかったのですが、今回はこれが妙によいなと思いました。
しゃがんで目線を画び正対させてじっくりと眺めてました。
なんだろう集中して見てるのにこの解脱する感は?
あと、フォンターナのナイフで切ったキャンバスのあの付き放された感はお見事。
絵画でもないしもちろん彫刻でもない。平面からの概念の乖離と物質の間で宙ぶらりんになる放置プレー、万歳!
![]()
そしてパウル・クレーも。
線と色彩に詩情が載って響いてる。
寓意と遊びでこさえてるんだけどもやはりこの豊かなバリエーションには参りましたってなってしまう。
![]()
アンリ・ルソー「第22回アンデパンダン展に参加するよう芸術家達を導く自由の女神」
このフラット感のある画面、たまりませんね。
奥行きも描かれているもののやはりどこかのっぺりとしてて一目でルソーって分かる安心感。
第一部だけでかなりのボリューム。
第二部はかなり時間をかけて見ないと書けないくらい。
原爆、戦後からの流れと美術を追う試みの展示はそうそうお目にかかれない。
冒頭から被爆された方の写真にガツンとやられた。
土門拳の写真。
絵画では中村宏の「砂川五番」、山下菊二の「新ニッポン物語」の力強い表現が印象に残りました。
「砂川五番」は初見でノックアウトされた覚えがあります。
基地に反対する彼岸と此岸。おかしなパースペクティブ、小さい坊さん。
「新ニッポン物語」の戯画化されてはいるものの浮かびあがるグロテスクな表現はむしろ直接に描かれた表現よりもぐっときてしまう。
河原温の「浴室」は見てて気持悪くなるのだけどもこのバリエーション、変節の表現は必見。
第二部は内容が広すぎて印象に残った部分のみ挙げてみました。
この「美術にぶるっ!」は東京国立近代美術館の本気具合の伝わってくる内容だと思いました。
収蔵を大切にする姿勢に好感を覚えますね。
1/14まで。必見です!




 SONY Cyber-shot HX30V (1820万/光学x20) ブラウンクリエーター情報なしソニー
SONY Cyber-shot HX30V (1820万/光学x20) ブラウンクリエーター情報なしソニー